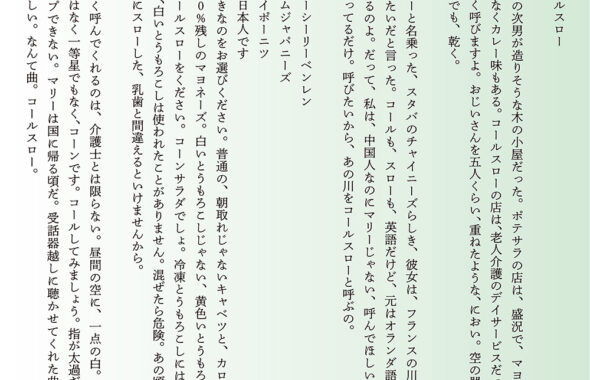小説「返す空に沈めて」南田偵一
航空を妨げるパラグライダーは、モノクロームに消えてゆく。沙都子の差し出す画面には、いよいよ砂粒がまぶされ、ふりかけを思わせた。
「ここが海だって誰がわかると思う」
画面にはさっき撮った白黒の一色海岸の砂浜が写っている、らしい。彼女がスマホを構えていた残像は、僕の頭にはかけらもない。
「毎年一度は来るの」
ここに来たいと言ったのは沙都子だった。運動を一切しない彼女の言葉を受け入れるのに時間がかかった。まだ下着姿を見たことがない。先に水着姿を見るのは正しい摂理に思えた。
が、沙都子は海開きの前を指定した。誰もいない海が見たい。サーファーが一人でもいたらどうするの、と聞けば、「沈める」。
沙都子の濃い眉毛を、いつになったら撫ぜることができるのだろう。会うたび一度は考えるようになった。
逗子海岸まで電車でやってきて、そこからバスに乗る。海開きの前だからか、乗っているのは老人が多かった。
バスは緩やかな坂道を上り、海岸線を舐めるようにくねる。細長い車体は唸るというよりあくびする感じで、民家の並ぶ細いカーブを曲がる。海の先に白い建物が見え、沙都子は、
「あそこの絵を観たことない。料理を食べただけ」
と聞いてもいないのにこぼした。いつの間にか彼女の口臭はミントの香りがした。麦わら帽子は、あのヒット曲のせいで恥ずかしい。彼女はそう付け足して、被っていたそれをバスの窓から放る。
見送る僕の項に鋭い痛みが走った。ゴムで弾かれたようだった。
「浜に着いたら冷たい強炭酸飲みたいね」
僕は首をさすり頷いた。意外だった。彼女は浜などと言わず砂浜と言う人間だと思っていた。
乗客はちらちらし、一色海岸では僕らしか降りなかった。
三十分くらいして、沙都子は僕にさっきの白黒の写真を見せてきたのだ。
彼女は笑って、浜を駆ける。追うべきかどうか惑ううちに、沙都子に太陽がまとわりついた。白いワンピースに彼女の肌が透ける。どうやら水着は着ていない。ブラジャーの白さと胸の膨らみに、軽く嫉妬した。沙都子の下腹部は薄く靄がかっている。沙都子の陰毛だとわかった。最初からなのか、彼女はパンツを穿いてこなかったのか。そういう話をしたこともなく、僕と出会う前から彼女はパンツを穿かない人間だったのか。それともいつの間にか脱いだのかもしれない。
僕の両方の手は、両方の足を覆っている白い靴と白いソックスを脱がした。電車に乗る前、沙都子は真っ白な僕の靴を踏んづけた。偶然ではない証拠に、一度踏んだあと、足型を取るように踏ん張ったのだから。
素足になった途端、ようやく人間になれた気がした。僕の前を駆ける女は、疾うに人間となり、止めない限り、もう一段上の人間になってしまう。僕の裸の足は砂に、行かないでくれ、といちいち引き止められながらも、沙都子を追いかけようとし、ちくっとした痛みを覚えた。砂が笑っている。
首の痛みを思い出した。
ああ、あのときか。麦わら帽子と一緒に窓から放ってしまったのか。
僕の首は捻れた。沖の方でサーファーが波を待っている。十人はいそうだ。
みんな沈めるつもりなのか、と少し大きな声を出した。
「沈める。だから手伝って」
僕は一度足の裏を見た。ちょうど中央辺りが赤黒くなっている。
浜を走った。先の空にパラグライダーが浮いている。あれはずっと最初からモノクロームだった、らしい。
「DayArt」の編集長自らが取材・体験し、執筆しています。