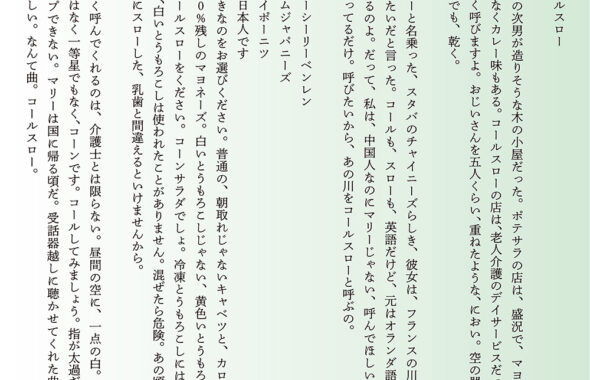小説「産みびらき」にゃんしー
姉の出発まぎわだった、泣きたくなるようなハッカ色の梅雨空、高校のショートホームルームを抜け出した帰りみち、旧国道に錆び付いた自転車を立ち漕ぎで走らせ、町でいちばん大きな郵便局に飛び込む。呼吸も整わないまま「葉書の束を買えるだけください」と、田舎町らしい寂れた受付のあおいツブ高のコイントレイに財布の中身をぶちまければ、「かもめーる」という絵入り葉書がおもむろに顔をのぞかせた。花火や西瓜、風鈴など、夏を思わせる水彩画が裏面にプリントされており、強張っていたのどの奥からほっと湿り気のある息がもれる。ふつうの郵便葉書と同じ値段で買えるそうだ。在庫が余り無く、けっきょく買えたのは三十数枚だけだったが、姉の出産予定日まで一ヶ月程度と聴いていたため、まにあうだろう。すぐに「かもめーる」を学生鞄の底にしずめ、また全力でぎりぎりのペダルを踏んだ。汗だくで家の庭にすべりこむと、姉はホンダの黒いワゴンの後部座席にすわらされ、去っていくところだった。運転席には地理の教科書でみたプランテーションの農夫を思わせるほど浅黒く日焼けしたおばさんがハンドルを握っていて、姉いわく「施設のひと」だという彼女は、嫌になるぐらいいやみのない笑顔でしわだらけの右手をかろやかに動かし、後部座席のウインドウをがああと下げてくれた。冷房が効いていたのか、すっきりした空気が溢れてきたけれど、僕の知る姉のナツメヤシみたいな匂いは諦めたかのように消えている。彼女が泣いていたとき、かけられた言葉はないのだから、彼女が泣いていないいま、かけられる言葉は見つからなかった。でもきっと次に会ったとき、出産を終えた彼女は僕の知る姉ではなくて、もうこのひとと話せる機会は二度とこない。しかし黙ったまま「かもめーる」の束を渡し、それきりだ。
ポストには毎日「かもめーる」が届いて、日々のたのしみになった。文面には何も書いておらず、夏らしいさわやかな絵柄だけがまぬけに笑っている。かなしいぐらいイノセントなその風景に上書きできる言葉はやはり無かったのかもしれない。あのときの「ごめんね」がわだかまる。大人びた珈琲のようにふかかった夜のおわり、子どもの名前を姉に尋ねてみたが、養子に出されるのだから名前を付けても意味がないと、据わった面差しはきっと名前を考えていたのだろう、意味とはなんだったのか。宛名面には鉛筆の手書きでうちの住所と僕の名前が姉らしい筆圧のつよい字で刻まれている。毎日とどくその文字のわずかな変化だけで僕は姉の暮らしを想像した。よく知るはずのうちの住所を毎日書く姉の心境を思うだけで、いくらでも僕は彼女に愛しくなれて、毎日書かれる僕の名前を思うとき、そこにまだいない誰かに狂おしく嫉妬してしまう。葉書からは海の匂いがする、「施設のひと」が斡旋してくれた病院は、海のそばにあるのだろうか。
姉から届いたさいごの葉書には、はじめて文面にたよりない文字が歪んでいた。たすけを求めるようなほそっこい行書体で「七月二十三日」とぬれた線をひいている。ああ、うみの日だ。病院の名前も住所も聴かされておらず、葉書にも書かれていなかったし、僕はどこにも行けないのだと葉書をつよく握りしめれば、黒くかすれた「鞆の浦」の消印があわれ海月のように滲んでいく。
「かもめーる」はその年で廃止され、姉から届いた葉書の束は輪ゴムで綴じたまま、机の引き出しの一番下の段でとべない羽根をふるわせている。「かもめーる」には当選番号が書かれており、賞品が当たることもあるらしいが、どんな賞品があるかは調べてないから分からない。もしもなにかと引き換えることができるなら、どんなものであれば僕はかもめの啼き声を手放せるだろう。子どもなんかいらなかった。あのころの、ナツメヤシの匂いがするおさない姉だけ、なつの初めに戻ってきてと思うけれど、書かれなかった言葉はひらかれた海の数センチうえを滑空していく。うぶごえのように。
「DayArt」の編集長自らが取材・体験し、執筆しています。