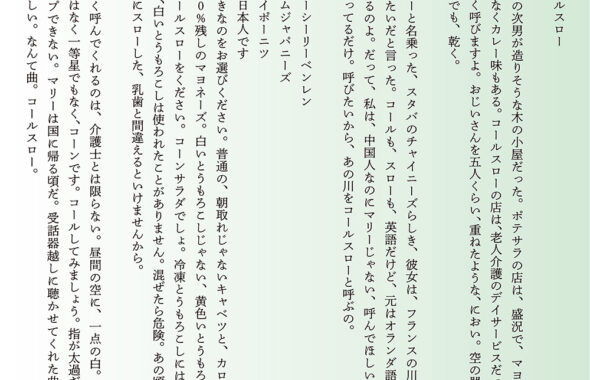小説「しよみ」南田偵一
徳島から引っ越してきました、三好です。
彼女は、テレビ放送の標準語で、自己紹介した。頭を綺麗に下げた。少し、茶色く、燻んだ髪。教室の窓から、先に、多摩川が見える。恥ずかしくなった。徳島には、四万十川が流れてるんだっけ。
一ヶ月も経たないうちに、
「吉野川」
三好は、呟いた。
なんでもよかった。きっと清流なのに、違いない。
「将軍、殺したんでしょ」
彼女は、声を出さず、頷いた。ミヨシナガヨシ、マツナガとヨシテル公、襲った。
「僕も殺してるんだ」
「誰を」
「ヨシノリ」
「赤松君やったっけ」
「せや」
四国も、関西弁、しゃべるんやな。つい、地の、言葉を吐いた。
二人で笑った。
さかさまから、読んだ遊び。いつまで、やるんやろ。大人んなって、会社に入っても、心ん中で、ぶつぶつゆうたりすんやろか。しよみ、赤松君は、つまかあ、なんか、きれ、悪いね。
土手にじかに、座ると、草の色がスカートに移ってまう。紺やから、同系色やから、大丈夫。座ったんとき、レモンの香料の匂いがした。スカートからか、スカートの中からか。三好の足首は、真冬、教室の机の脚のように、ひんやりした。
「東京も、灯りのないところ、あるんやね」
「なんも変わらんよ」
「赤松君も、関西から越してきたの」
兵庫・播磨から、都下の街に移ったのが、去年の夏やった。父は、将軍を殺した一族やゆうことを、なぜか誇りにしてた。時代が変われば、人殺したこと、えばれるんか。地方の支社から、栄転で東京本社に異動になったことが、父ちゃんはうれしゅうて、しゃーない。母も、ゆうておきながら、うれしそうやった。
「でも、また引っ越すん」
「どこへ」
「東北」
三好は、それ以上、聞いてこんかった。足首を撫で、ふくらはぎから、膝頭、腿までやっても、身じろぎひとつせんかった。将軍を、殺すって、そうゆうことか。
先祖は、元は、鹿浦ゆうた。時代が下って、なんやかの功績あったゆうんで、赤松姓をもろうた。ほんとは生粋の赤松の血ぃではない。父は、本社に移って早々、下剋上を果たそうと、上司と刺し違えた。母が、ゆってた。細かい事情はわからん。戦国の時代やないんやから、もっとうまく生きりゃええのに。
「うまく生きてたから、本社栄転やなかったの」
ツッコんでも、母は、笑いも否定もせんかった。
三好が、少し、膝を開いた。
「私、妊娠したんよ」
手が、止まった。「祖父ちゃんが、亀、獲ってくれたん。小学生んとき、吉野川で。持って帰ってきて、おっきな、使い古した火鉢んなか入れてたら、翌朝、いなくなってた」
おんなじ感覚やってん、堕ろしたとき。
彼岸の、マヨネーズ工場から、煙が昇る。ケチャップ工場やったらよかったのに。なんかイタリアっぽいし。キユーピーさんが色褪せてる。キユーピーさんって、大人になっても、キユーピーさんなんやろか。
酸っぱいにおいが漂ってきた気がしたら、三好の顔が、目の前にあった。おっぱいの匂いや思ってたんに。
「住めんようになって、こっち来たん」
無名白、って、知っとる? 知らん、何それ。科挙とかに受からんで、街さまよってる、一般の去勢人を、無名白ってゆうんやって。宦官のなり損ない。
「私、無名白やねん」
「世界史好きなんか」
「日本史も好き。理科は嫌いや。世界史、日本史、地理選択したった」
「先生、怒らんかった?」
科学なんて、なんも、救うてくれんし。
スカートの裾から、覗く、パンツは白かった。抱きついたまま、一緒になりたい、思った。一緒なって、ごろごろ転がって、多摩川んなか、放り込まれて、浮いて、沈んで、藻になってやりたい思った。
「ほなしよみ」
三好の唇は、レモンの味なんてせんかった。
「子につけよう思ったん。なんか響き、かわいいし」
顔が離れてった。
三好は立ち上がった。スカートを、ぱん、と一回はたく。
「東北行っても、手紙書く」
「いまどき?」
「LINEつこうとらん」
「私もつこうてない」
歩きだしよる。
じゃあ、住んでるとこ、教えて。
教えん。
なんで。
無名白ゆうたでしょ。
さっきのなんやったん。なんで……
三好の血ぃやねん。
後ろ姿を、ずっと見てた。こっち向け、何度も念じたけど、三好は振り向いてくれんかった。土手を上がってゆくとき、膝に手、ついてた。女子高校生というより、おばちゃんに見えた。
サイクリングやランニングしてる人たちが行き交う。三好は、振り向いた。願いが叶った。暗がりで、ぼーっと、両手を、剣道の構えのようにして立った。振り上げて、斜めに空を切った。慌てて立ち上がる。
「や、ら、れ、た」
おのれ、三好め、裏切ったな。
自分でも信じられないくらい、涙が、あふれた。逆立ちしたら、止まるんやろか。
つまかあ。
えいやっと、両手を、力いっぱい、土の上に押しつける。勢いあまって、転がってしもうた。目ぇ回って、どっちが東か、西か、わからんようなった。
三好は、土手ん上で、ひとり笑ってた。
「DayArt」の編集長自らが取材・体験し、執筆しています。