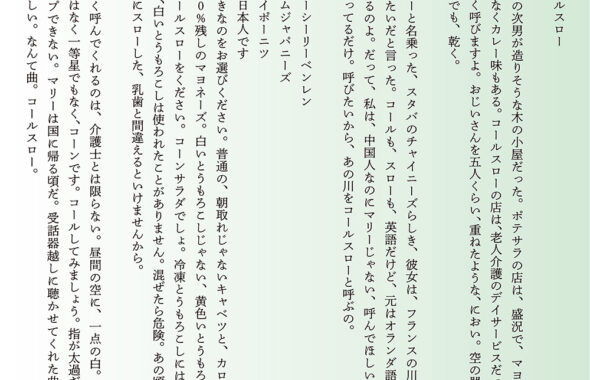小説「カノンさえ弾けなかった」旅田百子
夕飯の場が、緊急家族会議に食われた。
バラエティー番組から拍手が沸き起こった瞬間、父はリモコンのボタンを押し、私の視界と関心の中心を遮断してみせた。
「ピアノをどうするかを決める」
頭に大きな疑問符が浮かんで、父の隣に座る母へ目線を送ると、諦めたような微笑。
私は悟る。何も言い返さず、極力はやくこの時間を終わらせるのがいい。
「あんたが決めることじゃないでしょうよ」
しかし左から祖母の強い声。
「母さんは典に甘すぎる」
「あたしが典ちゃんにあげたピアノなんだから」
「ピアノを勝手に辞めて帰ってきた典には、失ったものがある」
「回りくどい! そんなもの、あっても大したもんじゃないよ」
このまま論点がずれていって、有耶無耶に終わってくれないかな。薄っすらそんな期待をしながら、味噌汁のさつま芋が極力口に入らないよう箸で塞ぎ止めつつ、甘い汁を啜っていたら父と目が合ってしまった。
「お前は何で勝手にピアノ辞めてきた? バレエ、そろばん、スイミングもそう。これまでに何かひとつでも続けたことあったか?」
小学校にはもう五年通い続けているよお父さん、と咄嗟に反論しかけたが、やめた。箸が飛んできそうな勢いだし。
「ピアノは四年続けたじゃない」
母の呟きが、アルミホイルの中で湯気を失っていく鮭やきのこの上に落ちた。
「四年? 四年も続けたか?」
「続けたよ」知らなかったの?
「お前は四年続けたものを、親に断りもなく辞めて帰ってきたんか。そのことで、お前は親と先生からの信頼を失って、親も先生からの信頼を失ったのがわかるか?」
え、これ何の話? 私はサイコロでも振るように箸を放り、急いで顔を両手で覆った。不本意ではあるけれど、簡単な努力ならする。
「ごめんなさい」
お腹空いてるのに、と思いながら、涙を拭うような素振りを続けていたら「典ちゃん、ピアノは売らないから、大丈夫だからご飯食べな」と祖母が結論を出してくれた。父は何も言わなかった。バラエティー番組が復活した。
冷め切った夕飯の後、客間へ行き、これ見よがしにピアノを弾く。午後六時半以降は弾かない決まりになっていたけれど。
「典ちゃん、八時だから。もう終わりよ」
ドアが開いて、祖母が顔を覗かせていた。
「じゃあ最後、一回だけ弾くから聴いて」
楽譜を最初のページまで戻す。左手の指を鍵盤のレとレに、右手の指はファのシャープとファのシャープの上に置いた。振り返り、祖母がソファに座るまで見届ける。それから向き直って、息を深く吸って、吐いた。
所々つまずきながら約三分半。
「ここまでしか弾けない」
「上手よ。ずっと聴いていたいくらい」
「次の発表会で弾く予定だったの」
「あらまあ、それは残念」
軽やかな口調だった。いつだって、私の味方になってくれた人。
指紋で汚さぬよう意識しつつ、そおっとピアノの蓋を閉めたら祖母の隣へ行く。
「さっきのあれ、嘘泣きだよ」
「あら、泣いてなかったの」
「泣くわけないよ。典ちゃん、むしろ笑いそうになって困った」
丸い肩に両腕を回して、庇うみたいに祖母を抱きしめた。年寄りの骨は心許ないから、力は込めず、寄りかかることもせずに。
「典ちゃんは女優さんね」
私の腕をあやすみたいにたたいたり撫でたりする祖母の、紫色のカーディガンに鼻を埋めると防虫剤のにおいがした。
祖母の身体の質感が好きだった。見るだけで触るだけで、私をうんと小さかった頃に戻すことも、突如大人に変えてしまうこともできる質感。
そんなことを思い出した二十二歳の夜、携帯電話越しの父が宣言した。
「ピアノを売る」
馬鹿も休み休み言ってほしい。あなた、完全に部外者でしょ。
「ピアノを売ったら一生許さない」
思いきり雑に画面を押し、そのままベッドめがけて携帯を投げつけた。床でもテーブルでもなく、ベッドに。そんな自分の冷静さに軽く失望して、一生許さない、なんて小学生のための台詞だよねと少し笑った。
ピアノが消えた客間を想像する。
そこだけ壁紙の色が違っている。
今はないあの時間を、守ることはできるだろうか。
息を深く吸って吐くと、携帯を拾い上げた。
(了)
「DayArt」の編集長自らが取材・体験し、執筆しています。