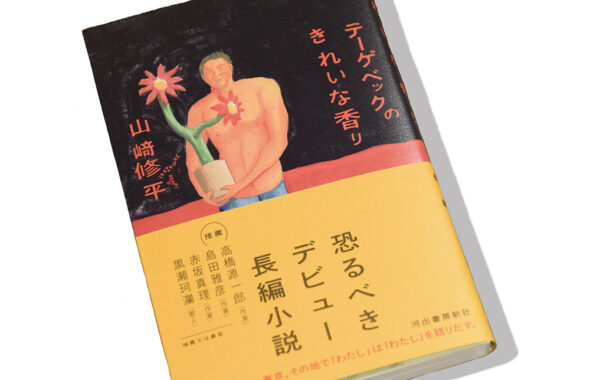「DayArt」27号特集「追悼 林聖子」
風紋は1961(昭和36)年にオープンする。閉幕した際の店は3代目で、僕が初めて訪れたのもここだ。
地下へ通ずる階段には赤い絨毯が敷かれている。昔はコンクリートが剥き出しだったが、かの竹内好(中国文学者)が転落したことで敷かれるようになったという。

写真:石本卓史
ちなみに階段を下り、正面の黒いドアの脇に蛙をモチーフとしたランプがあった。あれは僕がかつてプレゼントしたものだ。店内にある時計もそう。いつ行っても、飾ってあって我が家に帰った気分になった。
ドキドキしながらドアを開く。一面黒のモダンな壁、抑えられた橙色の灯り。カウンターに立つ髭の男性(ご子息の卓さん)が「いらっしゃいませ」と口にするものの、一瞬不審そうにギロっと見る。
改めて用件を告げると男性の顔は綻び、「ママ」と裏に声をかける。着物姿の女性が扉から出てきた。
「ああ、よくおいでくださいました」
単なる学生に頭を下げてくださり、名刺をいただく。初めての経験だった。
まだお客さんはおらず、奥のボックス席に座らせてもらった。カウンターの脇に本棚がある。目を凝らし、背表紙をざっと見やると、重々しい名前が連なっている。改めて背筋を伸ばしていると、聖子さんがお盆にビールを注いで持って来てくれた。
「どうぞ召し上がって」
「ありがとうございます」
僕は、完全なる下戸だ。不勉強な人間なので、風紋に通いつつも、結局は酒飲みになれなかった。下戸の常連客は僕ぐらいだったのではないか。
この日のことは、いつまでも覚えている。胸の高鳴り、掌の汗、喉の渇き、いつだって鮮やかで、瑞々しい。
聖子さんは二時間くらい、僕の質問に応じてくれた。推測が入るが、聖子さんは太宰があのとき、進んで玉川上水に入水したと思っていなかったようだ。
「私の母(秋田富子)がこの頃の太宰さんは危ない。死んでしまう気がすると予感していました。その話をどこからか聞かれたようで、あるとき太宰さんが仰ったの。聖子ちゃん、僕は死なないよ、あの子を残して」
あの子とは、太宰の長男のこと。聖子さんは太宰の言葉は嘘ではないと確信していた。そんな太宰さんが自殺などするはずがないと。
あっという間に時間が経ち、お礼を言ってお勘定をしようとすると、
「お代は結構ですよ。私の奢り」
聖子さんは、初めてとっつきやすい笑みを浮かべてくれた。
卒論が完成したら、また来ます、と約束し帰路につく。
興奮で、どう新宿駅まで歩いたのかわからない。太宰と親交のあった人と話せた。間違いなく、僕は聖子さんの背後に、言葉に、太宰を思い浮かべていた。
「DayArt」の編集長自らが取材・体験し、執筆しています。