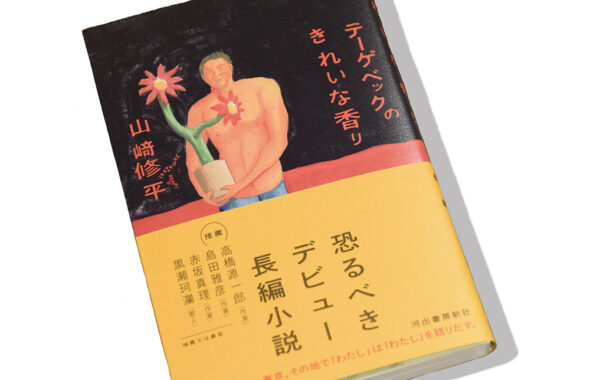第2回「食って寝て本を読む日々」(山﨑修平)
某月某日
有り難いことに詩集『ダンスする食う寝る』が舞踏の舞台となった。所謂現代舞踏には疎く、当日までどのようなかたちになるのか予想もつかなかったが、素晴らしい公演にしていただいた。詩を舞踏の舞台にするということは、言語である詩を非言語であるフィジカルなものへと翻訳するということだ。図らずも先述した吉田健一展のことを考えずにはいられなかった。詩人の友人は、私の詩がどのように舞踏になるか興味深かったらしいが、舞踏家は同じプロセスを異なる視点で見ていただろう。そもそも詩というものが、言語によって言語ならざるものを翻訳している、そんな向きもあるだろう。
舞踏は遊舞舎という新進気鋭の二人によるユニットによるもの。岩手の遠野の民俗舞踏など、各地の伝統的な舞踏を吸収しながら新たな解釈を施し、現代に通じる舞踏を模索していらっしゃる。ご興味があればぜひ公演情報をチェックし、足をお運びください。
Twitter@yubusha_butoh
某月某日
ゆっくりと本を読む時間がない中で読む本は、強烈な印象を残すものが多いのは何故だろう。
まずは、髙草木倫太郎さんの詩集『電解質のコラージュ』(七月堂)がとても良かった。現代詩として解される詩は、とかく難解で読者を選ぶと言われるが、それは語句の意味に拘泥し、物語として捉えようとしているからで、詩をそのまま言葉の連なりを愉しむものと受け取れば、実に素直に「読める」詩集が多い。この詩集の「A Day in the Life」では、「私はプラスチックの椅子から見える風景に/この上なく素晴らしい残酷を見た/それは私を突き刺し、そこから動けなくする」という詩句が非凡だ。こうした直訳調の硬い文体は、「プラスチック」という人工物の冷ややかなものの表し方として優れているし、「私」という主体の捩れや歪みを直截に「見た」とする鮮やかさは、これまでにない詩の現れを感じさせた。
吉行淳之介の『星と月は天の穴』(講談社)は、会話文に匂いがあって良い。匂い。つまり口臭や体臭、盛り場の饐えた匂い/臭いのことである。日常的にマスクをする生活がもう二年半続くわけだけれど、この二年半は嗅覚を塞いで街を歩いているということでもある。渋谷駅の、今は渋谷ストリームになっている辺りは、夏の驟雨(しゅうう)のあとには鼻をつんざくような悪臭が渋谷川から流れてきた。街は斯様に浄化され匂いは取り除かれてゆくのは、衛生上、或いは商業上当然のことではあるだろう。しかしながら、どこか寂しく感じてしまうのは何故だろう。煌びやかなカタログを観ているような現実感のない浮遊した街のように感じてしまうのは何故だろう。吉行淳之介の小説は、どの小説にも戦後荒廃期から立ち直る人間の匂いがする。その匂いを忘れてはならないと思う。