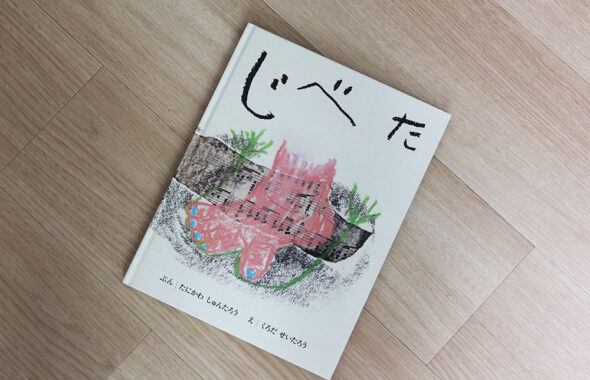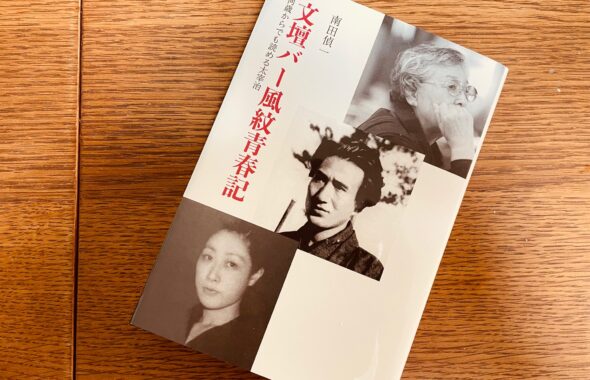『都電物語』(虹色社)
『都電物語 荒川線 Photos&Novels』虹色社/2,200円(税別)
都電が初めて開通したのは、1911(明治44)年。その後、次々と廃線となり、残されたのが「荒川線」(東京さくらトラム)だ。
本書は、三ノ輪橋駅〜早稲田駅の全区間を6区間に分け、それぞれの区間を舞台にした小説と写真で構成されている。
以下、各作品の寸評となる(敬称略)。
■「たゆたうだけでなく」熨斗克信 〈三ノ輪橋〜町屋〉
法事で実家に帰った、主婦の弥生は迷っていた。久しぶりに会った友人の瑞紀から、一緒に仕事をやらないか、と誘われていたからだ。
本作品において、弥生がどう決断したのかがクライマックスの鍵となる。個人的には、いとも簡単に流れやすい決断を、書き手の熨斗がぐっと堪え、試行錯誤した上で物語を締めたように感じられた。
もっと簡単な決断(小説の結末)はあったはずだ。しかし、熨斗はその流れに乗らず、弥生という一人の女性の身になって考えた。その過程というものが感じられた。本作品を一筋縄でいかない、丁寧に書かれた小説に昇華することができた所以であろう。
細かい描写、練られた文体、しっかり考えられた言葉選びは好印象だった。
■「熊野前まで」齊藤圭介 〈町屋二丁目〜小台〉
齊木珪蔵は、若い噺家である。そのためか、文体はどこか近代文学の香りがする。実際、本文には葛西善蔵などの名前が登場する。
齊木は落語の稽古に身が入らない日々を送っていた。10年以上の付き合いとなる友人・野瀬に、落語をやめることを漏らすが、「やめないだろ、どうせ」と軽くいなされる。
喫茶店「ロンリイ」での二人の会話シーンが多く描かれているのだが、実に軽妙である。太宰治の「人間失格」の葉蔵と堀木の会話を彷彿させるところがある。
途中、「燐寸」を「りんすう」と読むくだりがあるのだが、実にうまかった。個人的には「りんすう」というタイトルを付けたくなってしまう。
ラストは清々しい。都電と徒歩の速度で、東京が描かれている。
■「夏の街から」長谷川美緒 〈荒川遊園地前〜飛鳥山〉
高校生の千紗は、進路に迷っていた。幼少の頃、よく遊んでくれた叔母・みやこが住む飛鳥山を訪れる。
みやこは昔、交際していた川崎と別れていた。千紗は、なぜ二人が別れたのかを知ってしまう。
二人の感性はどこか似ており、みやこは都電を「幽霊」や「生き物」と捉える。のっそりと生きていた二人は、あたかものんびり走る都電のようだった。
だが、決断は急激に訪れる。ラスト、二人は「生き物」に引きずられるかのように、それぞれの決断をしてゆく。その決断は、二人にとってレールからの脱線かもしれない。
短編ながらも、緩急を織り交ぜて描かれている好編。
■「まだ曇り」長藤彬 〈滝野川一丁目〜大塚前〉
雄平と佳奈は交際しており、結婚を考えていた。だが、苗字を変えたくない、という理由もあって事実婚を選ぶ。二人は両親に挨拶と報告のため、佳奈の故郷へ赴く。
「二人とも、もう大人なんだから」
義父(佳奈の父)のこの言葉は、いかようにも解釈できる。路面電車が住宅街を抜けるように、都会の街並みを抜けるように、人生の径もひとつではない。
義父は、二人の背中を押したのだろう。だが、雄平はそれをどう受け取ったのか。「まだ曇り」とは、これから晴れとも、雨とも予感させる言葉である。実に象徴的なタイトルだ。
■「チェック・アラウンド」栗山直樹 〈向原〜鬼子母神前〉
今回の区割りの中で、個人的には最も難しかったのではないかと思う。なぜなら、この区間には池袋が含まれているから。あの巨大都市・池袋と都電、なんともミスマッチである。
確かに、雑司ヶ谷や鬼子母神といった昔ながらの風情を残すエリアではある。書き手の栗山は、どこを物語の舞台にするのか、腕を試されるとも言える。
物語は、ポーカーのディーラーが主人公である。彼はラスベガスから池袋に帰ってきたのだが、どう生きたいのか迷っている。
雑司ヶ谷霊園付近で、主人公は恋人の飼い猫ジローと似た猫と遭遇する。ジローは逃げてしまっていたのだ。そのシーンは、どこかかつての自分の姿を探し求めているかのようで印象的だ。
ギラギラした都会と都電のコントラスト。栗原は難しい区間をしっかりと新旧の街を捉えることで、好編に仕上げていた。
■「ここは春」上條和佳奈 〈学習院下〜早稲田〉
最後を締めるのにふさわしい作品だ。
10年住んだアパートの取り壊しのため、「わたし」は引っ越さないとならない。淡々とした日常の中に、特別な出来事は起こらない。同じアパートに住んでいる「皆月」や大家とも、淡々と別れていく。
しかし、そこに上條の巧さが潜んでいる。「わたし」の目にするもの、感じるもの、すべてが鋭敏である。それでいて、感情はしっかり抑制されている。
ずっと読んでいたい。心がくすぐられる文体。個人的には、ベストの作品だった。
駆け足になったが、それぞれの作品の寸評を述べた。冒頭の熨斗、ラストの上條の小説は、いずれも春の季節。各小説の登場人物の物語は、同時進行で繰り広げられているのかもしれない。
それは、現実の世界を生きる我々にも言えることだ。今、大事な誰かは、同じ時間、違う場所で喜んでいるかもしれない。あるいは、悲しんでいるかもしれない。しかし、淡々と人生は進んでいく。都電がゆっくり進むように。
本書内には、何枚もの写真が収められ、マップも載っている。暖かい季節になったら、本書を手にして都電に乗って散策してみるのもいいだろう。
「DayArt」の編集長自らが取材・体験し、執筆しています。