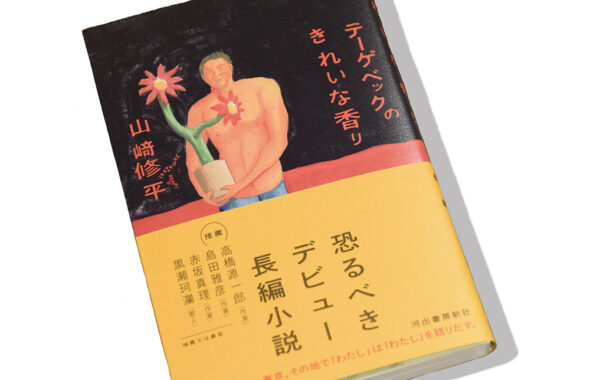第1回「食って寝て本を読む日々」(山﨑修平)
某月某日
アンナ・シャーマン『追憶の東京』(吉井智津訳、早川書房、二〇二〇年)を読む。東京のそれぞれの街−−日比谷や、根津、築地など、地名が章題になっている−−にまつわる記憶の束を繙(ひもと)く本だ。ふと、私は東京をどれほど分かっているだろうかと考えた。「東京」という語句を「日本」に置き換えてもいい。東京に生まれ育ったのだから、東京の内にあるのだと考えていると、袋小路に迷い込みそうだ。そもそも内と外とが判然としない。それは地政学的な境界ではなく。内と外とで波間を揺蕩う。外国文学としての日本文学の捉えかた。日本を、東京を、外から観てゆく。
昭文社から出た『東京のトリセツ2』。これを前掲の『追憶の東京』と併せて交互に読んでゆく。内からの余所者という屈折した視点。あるいは流浪する人という観点。分かることで分からないことが増えてゆく快感。

某月某日
中学・高校のときの部活に、目覚まし時計に使用するBGMをバッハのチェンバロ協奏曲第一番の一楽章(BWV1052)にしているという後輩がいた。他のいかなる曲、ロックもテクノも、裸足で逃げ出すくらい、チェンバロ協奏曲一番の目覚まし時計としての効果はてきめんだ。バッハもまさか目覚まし時計に自作曲が使われるとは、想像だにしなかっただろう。ただ、眠っている人を起こさせる「驚き」という要素は、音楽には不可欠なものであることは間違いではなさそうだ。
初台の東京オペラシティに赴き、バッハを聴く。三台のチェンバロによる繊細な音色は、弦楽器と混ざり合うことなく、儚げにコンサートホールに突き抜けて拡がる。「二台のチェンバロのための協奏曲BWV1060」を、先述した部活で演奏したことがあった。それゆえに、想い出の曲を生演奏で聴けることが実に嬉しかった。
そういえば初台も「台」であるように、高台の土地にある。甲州街道が尾根を縫うように続いていることが分かる。京王電車が路面であったころの形跡が残っている。ドイツゆかりのバッハを聴いたのだからと、終演後ドイツ料理の店に繰り出した。店へと歩みを進めながら、初「台」なのだから、ここからどういう道を選択しても、下り坂なのだろうなと考えていた。その予想は的中し、いささか食べ過ぎた重い身体は、下り坂の重力に抗うことなく、ドスドスと降りてゆく。チェロは、上昇スケールよりも、下降スケールの方が力強くて好きだと言っていた先輩がいたことを思い出した。元気にしているだろうか。