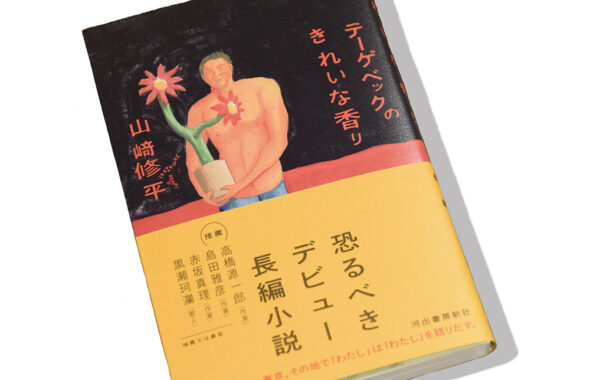第3回「食って寝て本を読む日々」(山﨑修平)
型というのは過去の経験という言葉とも置き換えられる。自分の経験ではなくとも、他者の経験や、書籍から得られたものも型を作ってゆく材料となる。自分から型に嵌ってゆき、型を活用し、型を強化してゆくことの心地よさもあることが解りながら、どこかにこの型を疑い、揺さぶることはできないかと思った……、というのがこの夏、何度となく考えていることだ。
或いは、速さ、早さ、というものへの危機感の表れかもしれないと思う。一冊の詩集を読む。何度も何度も読み返す。五年過ぎたあたりでようやく一つの感想のようなものが生まれる。けれどそれはまだ言葉になっていない。日々を散漫としかし確実に過ごし、言葉を育ててゆく。その後、五年、十年、二十年と時を経て、ようやく感想を話したい。詩集に限らず、自分が感受したものを安易に言語化したくない。してはならないとも思う。ニュースのミニコーナーにある、子供の芋掘り体験でのインタビューで「お芋掘れてどうでしたか」という問いへの「楽しかった」という答えのような、私たちの感情の言語化をどこまで研ぎ澄まされるべきなのか、考えてしまう。とはいえ、書評や批評という即時性が求められることがあるのも確かで、感情を拾い集めてゆくことをしながら、丸めてゆく、整えてゆく、ということを同時にしてゆく。

このような話をすると、所謂エクリチュールの話に留まることではないことも解る。テクストの上だけで話すことは、なにか「処置」を施しているとも思う。極めて社会的・政治的な論点とも重なる。混迷の世にあって、エネルギー効率の良い方策をとり、結論へと要約し、無駄を省く。このことの何が悪いかと問われれば、何も悪くはない。しかしながら、この早さ、速さそのものよりも、立ち止まり、振り返れなくなっていることに、危機感を覚えている。書くこと、というより、読むことの功罪を考えてしまう。昨今、批評が成立しなくなり、批評そのものの意義を問われるのは、私たちが考えなくなったからではなく、もはや悩めなくなったからだと思う。どんどん間違えましょう、過ちをおかしましょう、寄り道をしましょう、というのを喧伝するのは勇気がいることだが、型に嵌まっていることを甘受したくはない。